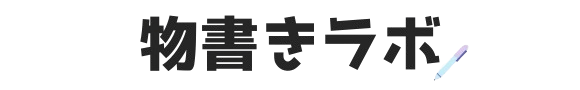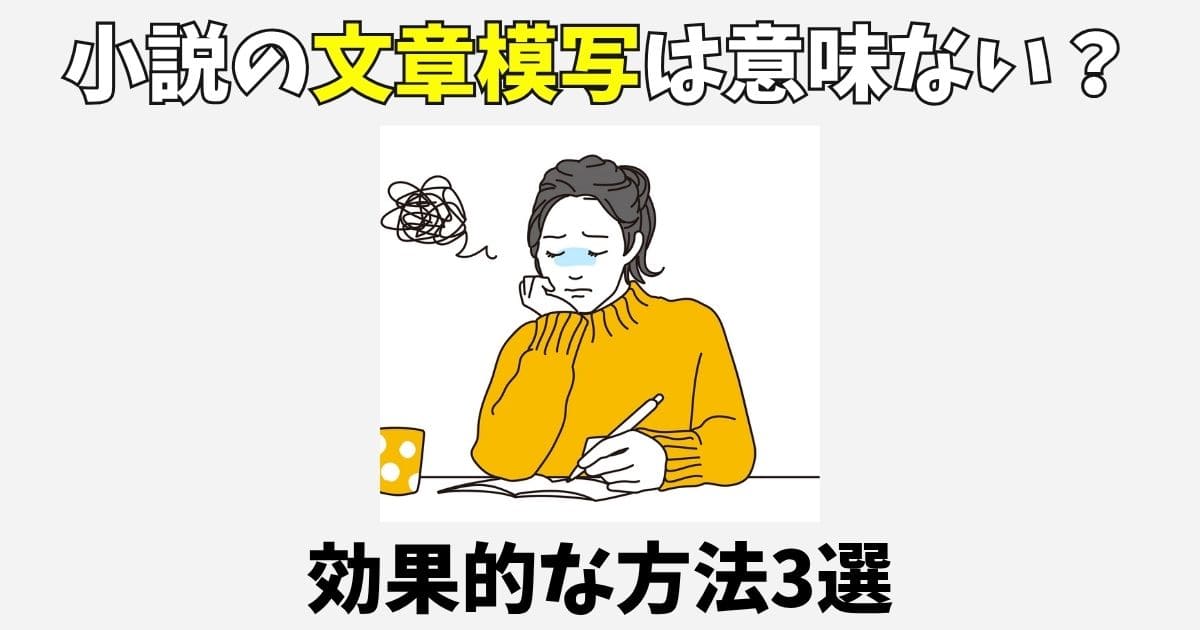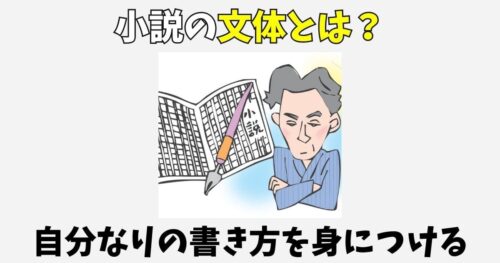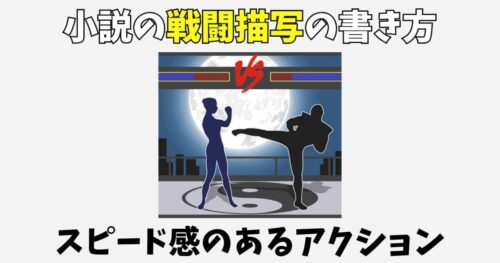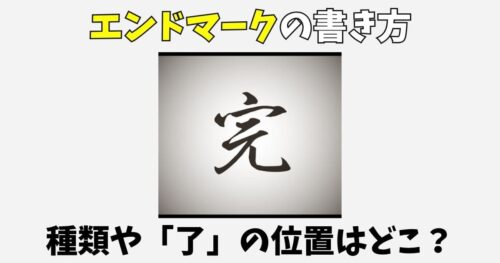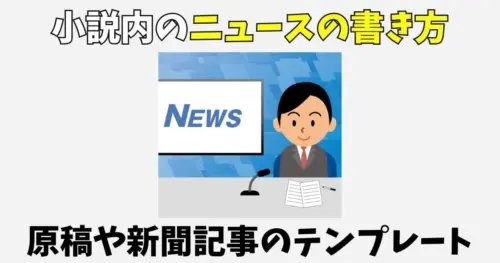文章上達法として「小説の模写」という方法を聞いたことがあると思います。
しかし、文章模写の効果について「書き写しは意味がない」という意見もあります。
私は正しいやり方を押さえれば文章が上手くなる効果があると思っています。
そこで今回は以下の内容でお届けします。
- 小説の文章模写は意味ない?効果がないダメなやり方
- 効果的な書き写し方法3選
小説の文章模写は意味ない?効果がないダメな書き写し
まずは小説の文章模写をするときに避けるべき、効果がないダメなやり方を解説します。
- ただ書き写すだけでは効果がない
- 模写が目的になると意味がない
- 意味を理解しながら書くことが大切
ただ書き写すだけでは効果がない
「模写は意味ない」と言われる理由のひとつが、やり方にあります。
たとえば、頭を使わずにただ文章を写しているだけでは効果は出ません。
小学生の宿題のように、漢字の書き取りのようにただ写しているだけでは全く効果はないのです。
文章は前後のつながりや構成が大切です。小説ならなおさら作家それぞれの表現や技術がたくさん使われています。
小説模写は、
- なぜこの表現を使ったのか
- この一文で何を伝えたいのか
など作者の意図を考えながら模写しないと、スキルにはつながりにくいんです。
逆に言えば、考える模写にすれば、効果はぐっと高まります。
模写が目的になると意味がない
もうひとつの落とし穴が「模写すること自体が目的になってしまう」ケースです。
模写はあくまで手段。目的は「小説力を上げる」ことですよね。
ところが模写を毎日のノルマにしてしまうと、いつの間にか「今日も1000字模写しなきゃ」と機械的になってしまうことがあります。
そうなると、どんなに時間をかけても得られるものは少なくなってしまうんです。
模写を練習として位置づけ「自分の創作にどう活かすか」を意識して取り組むことが大切です。
意味を理解しながら書くことが大切
模写を効果的にする最大のコツは「意味を理解しながら書くこと」です。
たとえば、ある登場人物のセリフや動作が、どういう感情の流れの中にあるのか。
描写の順番や言葉選びには、必ず意図があります。
それを読み取ろうという意識を持って模写すると、自然と「こういう書き方をすると読者に伝わるんだな」と気づけるようになります。
言い換えると、模写は受け身の作業ではなく能動的な読解トレーニングなんですね。
小説の文章模写は意味ない?効果的な書き写し方法3選
ここからは効果的でおすすめな小説の文章模写方法を解説していきます。
- いろんな小説の冒頭だけを模写する
- 文章や表現の意図を分析する
- 同じ設定で自分なりに描写してみる
いろんな小説の冒頭だけを模写する
文章模写の練習として、まず取り組みやすいのが「いろんな小説の冒頭だけを模写する」という方法です。
小説全文を丸ごと書き写すのは、かなり時間も根気も必要ですし途中で疲れてしまうこともありますよね。
ですが冒頭だけなら、短時間でも実践できて、しかも学べることがたくさん詰まっているんです。
というのも、小説の冒頭は作家が特に力を入れる部分だからです。
読者の心をつかむために、言葉選びやリズム、情報の順序など、さまざまな工夫が凝らされています。
たった1文や1段落で、物語の空気感や登場人物の雰囲気を伝える――そんな技がぎゅっと詰まっているのが冒頭部分なんですね。
たとえば、村上春樹さんの小説は冒頭から静かで不思議な空気に引き込まれることが多いです。
一方で伊坂幸太郎さんの作品はテンポよく会話や展開が始まりポップで軽やかな印象を与えます。
同じ書き出しでも作家ごとにまったく違う表現の工夫がされていて、それを比較しながら模写するだけでも多くの学びがあります。
冒頭模写のやり方
まずは気になる小説をいくつかピックアップして、そのうちの冒頭1~3段落をノートやパソコンに模写してみましょう。
ただの書き写しにならないよう、「どんな言葉選びをしている?」「どうやって読者の興味を引いている?」と考えながら進めるのがポイントです。
「この冒頭は視覚的な描写から始まっている」「あえて説明せず、余白を残している」など、気づいた点を1〜2行で書き出しておくと、後から見返したときに学びが深まります。
慣れてきたら、ジャンルや作家のスタイルを変えて模写してみるのもおすすめです。
文章や表現の意図を分析する
模写をするうえで、とても大切なのが「なぜこのように書いたのか?」という作者の意図を考えることです。
ただ写すだけの模写は作業になってしまい、時間はかけているのに身にならないというケースもあります。
でも、ひとつひとつの文章に「こう書いた理由があるはず」と目を向けるだけで、吸収できるものがまったく変わってくるんです。
たとえば、次のような文章を模写したとします。
「彼女は笑っていた。でも、その目はまったく笑っていなかった」
この文章、なんとなく書いているようでいて、実は細かい仕掛けがあるんです。
まず「笑っていた」のあとに「でも」と続けて対比が生まれていますよね。
さらに「その目はまったく笑っていなかった」という表現で、読者に「本心では違う感情がある」という違和感を与えています。
こうした表現技法は、模写するだけではなかなか気づけません。
でも、「なぜ目に注目しているのか?」「なぜでもで逆接を使っているのか?」という視点で見ていくと、その奥にある作家の意図や演出効果が見えてきます。
また、文章構造にも注目してみましょう。
- 一文がどのくらいの長さなのか
- 主語と述語の距離
- 修飾語の入り方
- 情報の順序
これらはすべて、読み手に伝わりやすくするための設計です。
たとえば、ある文章が短くテンポよく切ってある場合、それは会話や緊迫した場面を演出するためだったりします。
逆に、ゆっくりとしたリズムの長文であれば、情景描写や心情の余韻を伝えるためだったりしますよね。
このように、模写した文章に問いを投げかけることで、受け身の模写が能動的な学習に変わっていきます。
模写は作家の技術を写して学ぶこと。
でも本当に力になるのは、「どうしてこうなってるのか?」と考え抜いたその先にある、自分なりの答えなのです。
同じ設定で自分なりに描写してみる
小説の文章模写をする目的は、作家の技術を分析して身につけることです。
模写で学んだことを身につけるためには、実際に自分でも書いてみることが欠かせません。
なかでも特におすすめなのが、「模写した文章と同じようなシチュエーションや設定で、自分の言葉で描写してみる」方法です。
その雰囲気や描写技法を思い出しながら、今度は自分のキャラクターを使って、深夜のスーパーで似たような感情を描いてみようと挑戦してみる。
このように、学んだ型を自分の中で応用するトレーニングを積むと、模写の知識が自分の引き出しとしてしっかり根づいていくんです。
ポイントは、表現をまるごと真似るのではなく「学んだ技術をどう使うか」を意識すること。
たとえば、模写元で使われていた「短いセンテンスの連続で緊張感を出していた」「風景の描写で主人公の心理を代弁していた」といった要素を、自分の描写にも取り入れてみましょう。
最初はぎこちなく感じるかもしれませんが、それで大丈夫です。
「この感情、どうやって描けば読者に伝わるかな?」と考えながら書いていくうちに、少しずつ自分の文章が変わっていくのが実感できるはずです。
おすすめの流れは以下の通りです。
- 模写する(2〜3段落程度)
- 同じテーマ・設定で自分なりの描写を書く(300〜500字でもOK)
- 模写と自作を見比べて、違い・改善点・良かった点を書き出す
たったこれだけでも、毎日続ければ文章の精度はどんどん上がっていきます。
模写は真似るだけじゃなく活かすことでこそ価値がある。この考え方を意識してみてください。
小説の文章模写は意味ない?効果的な書き写し:まとめ
小説の文章模写は意味ないのか、効果的なやり方を解説しました。
何も考えずに写したり、模写が目的になっていると効果がありません。おすすめの方法は以下の通り。
- いろんな小説の冒頭だけ模写する
- 文章や表現の意図を分析する
- 学んだことを活かして自分なりに描写する
小説模写により作家の技術をインプットするだけではなく、しっかり吸収して自分の作品に活かせるようアウトプットすることが重要です