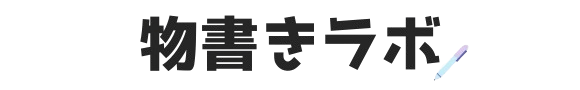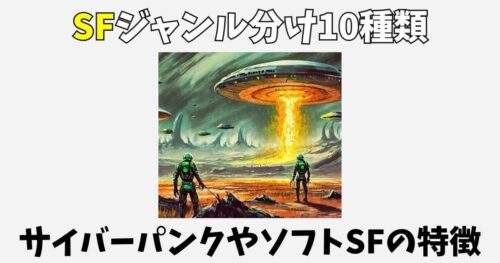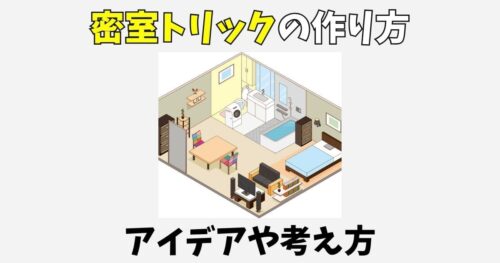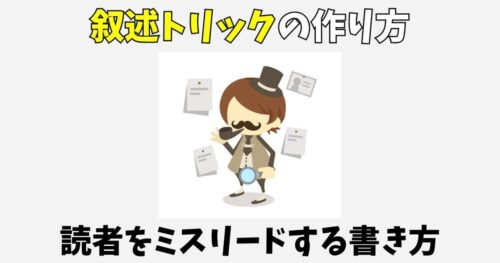ギャグ小説を書いてみたいけれど、どうすれば面白いコメディを書けるのかわからない……そんな悩みを持っていませんか?
この記事では、ギャグ小説の基本から初心者でもマネできるボケの構造まで解説しています。
- ギャグ小説の基本的な考え方
- コメディが難しい理由
- 参考になるおすすめ小説
- 作り方をパターンで解説
笑いの仕組みを学びながら、読者を楽しませるコメディ小説を書いてみましょう。
ギャグ小説の書き方!コメディが難しい理由とボケシーンの考え方
まずはギャグ小説を書くときの基本的な考え方について解説します。
- 笑いの型を知る
- キャラクターが大事
- セリフで笑わせる
- クスっと笑える小説を意識する
- ギャグ小説が難しい理由
- おすすめのコメディ小説
笑いの型を知る
笑いには基本的な型があるって知ってましたか?
コメディやギャグの笑いは何気ない日常から生まれることも多いんですが、以下の二大パターンがあります。
- 意表を突く(裏切り)
- 大げさにする(過剰)
例えば「Aだと思ったらBだった」っていう展開。
これ、いわゆる裏切りの笑いなんですね。読者が「こう来るだろう」と予想したところに、スッと違うオチをぶつける。これだけで笑いが生まれます。
もう一つは「大げさな表現」。現実ではありえないほどの反応や設定に、読者は思わずツッコミたくなる。これも笑いのスイッチです。
キャラクターが大事
コメディ小説で一番大事なのはキャラクターです。
ギャグはそのキャラだからこそ成立することがめちゃくちゃ多いんですよね。
たとえば、筋肉ムキムキの戦士が実はぬいぐるみマニアだったり、毒舌なヒロインがドジっ子だったり……。
そういうギャップが笑いの種になります。
逆に言えば、キャラが薄いと何をしても面白くなりません。「キャラが立ってる」というのは、コメディにおいて最強の武器になります。
まずは読者に「こいつ好きだな」と思わせるキャラを作ってみましょう。そこから笑いが自然に生まれますよ。
セリフで笑わせる
小説の笑いは地の文よりも「セリフ」によって生まれることが多いです。
反対に言えば、ツッコミやボケの突飛な発言などは会話のやり取りの中で映えるので、地の文で笑わせるのは難しいです。
そのためギャグ小説ではセリフのテンポ感が命。
間が悪いとスベるし、タイミングが合えばクスっと笑えるんです。
特におすすめなのは「ボケとツッコミの応酬」。リズムよくやり取りするだけで自然と笑える雰囲気ができます。
セリフのやりとりはお笑い芸人の漫才を参考にすると良いでしょう。
クスっと笑える小説を意識する
ギャグ小説やコメディを書くときに、声を出してゲラゲラ笑える作品を書こうとしていませんか?
それはプロでも難しいことです。小説は漫才やコントのように映像や喋りで笑わせることはできません。
文章だけで大爆笑させるようなことはかなりセンスが必要です。
そのためギャグ小説は、クスっと笑えることを意識して書きましょう。
ギャグ小説が難しい理由
コメディやギャグを小説で書くことが、他のジャンルに比べてかなり難しいです。
理由は以下の通り。
- 面白さは人それぞれで正解がない
- 内輪ネタになりがち
- 読者とのギャップが生まれやすい
- ボケとツッコミのバランスが難しい
- 笑いを説明するとスベる
正解がない
ギャグ小説が難しい一番の理由は正解がないこと。
ある人には大爆笑でも、別の人には「…なにこれ?」となってしまう。
読者のセンスや経験、タイミングに左右されやすく「誰にでもウケる」ギャグを書くのは難しいんですよね。
お笑い芸人のようなプロではない人がギャグやボケを作ろうとすると内輪ネタになちがりです。
仲間内しかわからないネタだと第三者が読んでも全く笑えません。
読者との間隔のズレ
次に多いのが読者との感覚のズレです。
書き手としては「ここ笑ってほしい」と思っても、読者にとっては唐突すぎたり逆にクドく感じたりすることがあります。
これは年齢層や文化背景、読書経験によっても変わります。
説明するとスベる
ボケや笑いの種を説明すると一気に寒くなるんです。
小説だと映像で伝えられない分、説明過多になりがちです。
たとえば「これが面白い理由は」と補足すると読者は一気に冷めます。
ギャグ小説は文章で説明するのではなくキャラのリアクションや状況で伝えることが大事です。
おすすめのコメディ小説
ギャグ小説を書くときの参考になるおすすめの小説を紹介します。
- 『イン・ザ・プール』奧田英朗
- 『太陽の塔』森見登美彦
- 『陽気なギャングが地球を回す』伊坂幸太郎
- 『オロロ畑でつかまえて』萩原浩
- 『怪笑小説』東野圭吾
伊坂幸太郎と森見登美彦はとにかくセリフやキャラ同士のやり取りが面白いです。
ぜひ読んでみてください。
ギャグ小説の書き方!コメディの作り方をパターンで解説
ここからは初心者でも真似できるギャグ小説の構造について解説します。
- 勘違い・すれ違いのパターン
- 天丼(繰り返し)のテクニック
- パロディを活かす
- 誇張と突飛な設定
- 緊張と緩和
- ギャップをつける
では、それぞれの構造をくわしく見ていきましょう。
勘違い・すれ違いのパターン
まず最も使いやすいギャグ構造が「勘違い・すれ違い」です。
たとえば、「告白されたと思ったら全然違う用件だった」とか、「AとBの会話の前提がズレていて話が噛み合わない」など。
読者は真実を知っていて、登場人物は誤解したまま進む。だからこそと心の中でツッコミを入れてしまい、笑ってしまうんですね。
天丼(繰り返し)のテクニック
テレビのバラエティ番組でもよく行われる「またそれやるのかよ」という笑い、それが天丼のテクニックです。
同じギャグやネタを繰り返し使うことで、1回目よりも2回目、3回目のほうが笑いが増すことも。
「キャラが何かのセリフを言うたびにオチでカレーを食べる」とか、「失敗の度に必ず同じ言い訳をする」など。
繰り返しには安心感と裏切りの期待があるんです。読者が「また来るぞ……」と予測して、そこでひとひねり加えると爆笑に。
やりすぎると飽きるので、3回目で変化を加えるとさらに効果的です。
パロディを活かす
元ネタがあるパロディは、読者が知っていればコメディとして威力抜群です。
- 有名なシーンをあえて崩す
- 名ゼリフをトンチンカンにする
など共通認識をいじると笑いが生まれやすくなります。
大事なのは、読者が元ネタを知っている前提を見極めることです。
マニアックすぎると逆効果なので、有名な作品やジャンルでやると成功しやすいです。
誇張と突飛な設定
現実ではありえないような「突飛すぎる設定」と「誇張表現」の組み合わせは、読者の想像力を超える笑いを生みます。
たとえば「体重1トンのアイドルがスキップするだけで地震が起きる」とか、「くしゃみ1回で異世界転生する」みたいな、ありえなさすぎて笑える設定。
誇張にはくだらなさが命です。「なんでそうなる?」というツッコミが自然に湧くような極端さを意識しましょう。
このタイプのギャグはラノベやライトギャグ小説と相性バツグンです。
細かい理屈より勢いと発想勝負で攻めてください。
緊張と緩和
緊張と緩和は吉本新喜劇でもよく使われる、ギャグの王道理論です。
人は緊張した状態が一気に崩れると、そこに安心と笑いが生まれるんですね。
たとえば、真剣な戦闘シーンの後に「腹減った…」とか、強面なのに声が女性のように高いなど。
重い空気や張り詰めたムードを一撃で崩すようなセリフや行動が、ギャップとして面白さを生み出します。
この空気の切り替えができると、読者の感情を揺さぶることができて印象に残る笑いになりますよ。
ギャップをつける
ギャグ小説でよく使われるのがキャラやシーンのギャップです。
たとえば、完璧なイケメンが「今日のパンツ、裏表逆だった」とか、女王様風キャラが「お化けだけはムリ」と泣き出すなど。
この落差は読者の期待を外してくれるので、笑いが自然に生まれるんですよね。
ギャップの作り方としては「強そう×弱点」「真面目×変な趣味」など、正反対の要素を混ぜるのがポイント。
意外性はいつの時代も笑いの本質です。だからギャップを意識したキャラづくりは、初心者にもオススメですよ。
ギャグ小説の書き方!コメディが難しい理由と考え方のパターン:まとめ
今回はギャグ小説の書き方を解説しました。
- 文章だけで伝えるギャグ小説は難しい
- 基本的な型やパターンを活用すると作りやすい
- キャラ立ちとセリフのやり取りを意識する
コメディ小説を面白くするには、ギャグの種類やストーリー展開を意識しながら、キャラクターの魅力を引き出すことが大切です。
今回紹介したテクニックを活用しながら、読者が思わず笑ってしまうようなコメディ小説を作ってみてください。