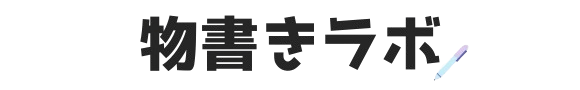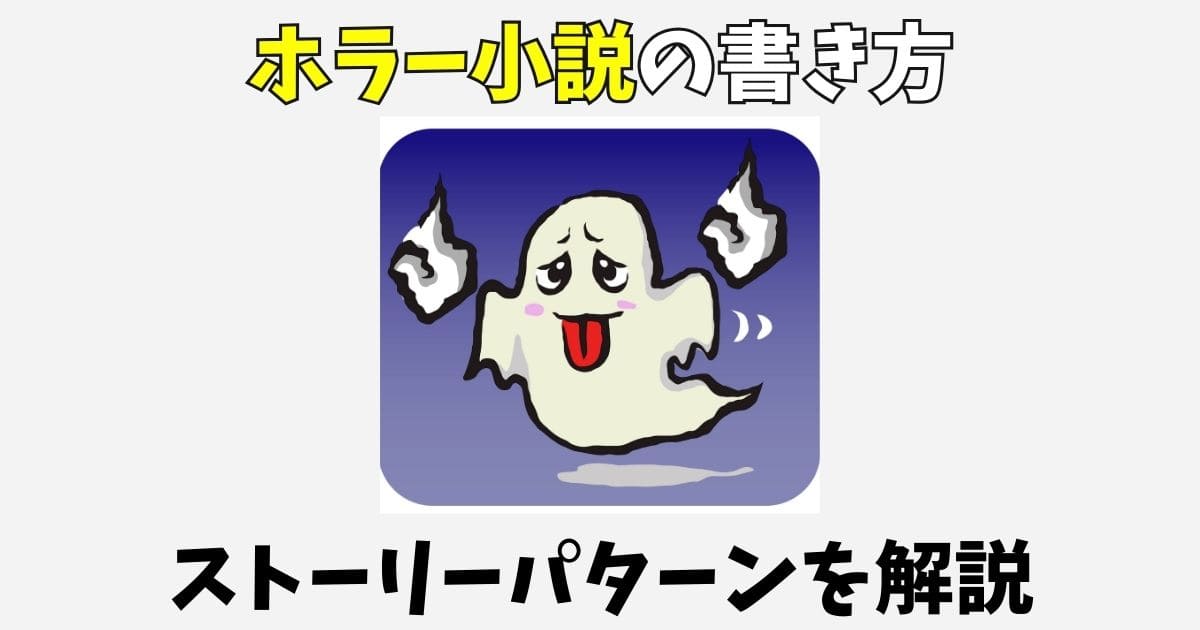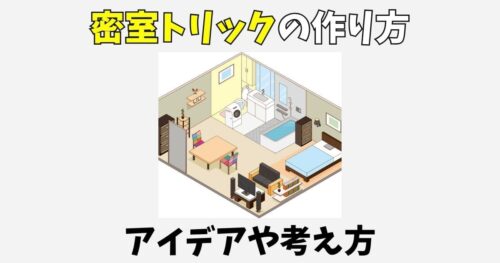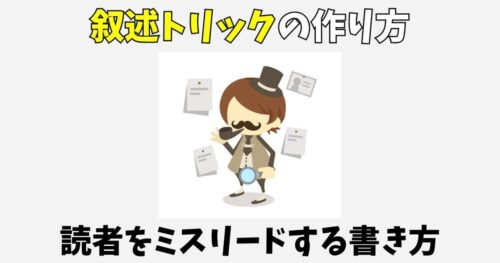「ホラー小説を書きたいけど、どうすれば本当に怖い話になるの?」
そんな悩みを持つ方のために、ホラー小説の基本ややらないほうがいいタブーを詳しく解説します。
怖いホラーを書くには、単に幽霊や怪物を登場させるだけでは足りません。読者が本当にゾッとするには心理的な恐怖やストーリー展開の工夫が必要です。
ホラー小説によるあるストーリーパターンを5つ紹介しているので、思いついたアイデアやネタを当てはめて完成させてみてください。
ホラー小説の書き方の基本を押さえよう
ホラー小説を書くには、基本となる要素をしっかり押さえておくことが大切です。
読者を怖がらせるためには、単に幽霊や怪物を登場させるだけではなく心理的な恐怖や日常の違和感を積み重ねていく工夫が必要になります。
まずは、ホラー小説を書くために重要な要素やテクニックについて詳しく解説していきます。
- ホラー小説に必要な要素とは?
- 心理的に怖さを感じさせる
- 読者が共感できる恐怖を描く
ホラー小説に必要な要素とは?
ホラー小説には、押さえておくべきいくつかの基本要素があります。
- 恐怖の対象(怪物・幽霊・人間の狂気など)
- 不安感や違和感の演出
- 読者の想像力を刺激する描写
- リアリティ
「何が」読者を怖がらせるのか、恐怖を感じる対象を明確にすることは第一にやらなくてはいけません。
そして恐怖を倍増させるための演出と描写。ここは小説家としての力量が問われる部分です。
ちょっとした異変を積み重ね、じわじわと恐怖を高めて読者自身に怖さを想像させること。「現実にありそう」と読者に思わせるための描写力が必要になります。
 三雲ハル
三雲ハルこれらが揃っていると、読者は「怖い」と感じやすくなります。
ホラーは「得体の知れないもの」に対する恐怖が鍵になります。そのため、最初から全てを説明せず、徐々に読者の不安を煽っていく構成が効果的です。
心理的に怖さを感じさせる
映画とは違いホラー小説では視覚的な強さや、ジャンプスケアと呼ばれる突然びっくりする出来事を仕掛けることはできません。
そのため視覚的な怖さだけでなく、読者の心理に働きかけることが重要になります。
ジャンプスケアとは、いきなり大きな音が鳴ったり、お化けが飛び出てくるなどのいわゆるびっくり演出のこと。映画やゲームでよく使われています。
心理的な恐怖を描くには以下の点を意識してみましょう。
- 未知の恐怖を描く
- 暗示と想像させる
- 音や気配の演出
- 日常の中の違和感
人間は正体不明のものに対して恐怖を感じやすいため、単に「怖い出来事」を描くのではなく、「なにかいるかもしれない」という状況を作ることで読者をゾクッとさせることができます。
読者が共感できる恐怖を描く
ホラー小説で重要なのは、読者が「自分にも起こりそう」と思える恐怖を描くことです。
以下のようなテーマは多くの人が共感しやすいです。
- 子供の頃の怖い体験
- 人間関係の崩壊
- 現実にありそうな都市伝説
大人になってからは平気でも、子供の頃は些細なことに恐怖を感じていましたよね。
暗い部屋や人形、押し入れの中など、誰もが一度は恐怖を感じたことがあるものを描くと共感されやすくなります。
また信頼していた人が豹変する、家族が恐怖の対象になるなど人間関係の崩壊は社会人にとって心理的に怖い状況です。
読者が「これはフィクションだから関係ない」と思ってしまうと怖さが半減します。自分にも起こりうると感じさせることで、よりリアルな恐怖を与えることができます。
ホラー小説のアイデア・ストーリーパターン5選
ホラー小説にはいくつかの定番パターンがあります。どのパターンを選ぶかで、物語の雰囲気や恐怖の種類が変わってきます。



思いついたアイデアを物語の落とし込めない場合は、これから紹介するパターンに当てはめて考えてみてください。
ここでは、特に人気があり多くのホラー作品で使われている5つのストーリーパターンを紹介します。
- 閉鎖空間:逃げられない恐怖
- 怪異との遭遇:理解不能な存在
- 呪いや因縁:過去が生む恐怖
- 精神が歪んでいく:正気を失う恐ろしさ
- 日常の崩壊:いつもの世界が壊れる
閉鎖空間:逃げられない恐怖
ホラーでよく使われるのが、「逃げ場のない空間」での恐怖です。
閉じ込められた状態で怪異に襲われたり、脱出できない状況が続くことで読者に圧迫感と恐怖を与えます。
たとえば以下のようなシチュエーションが考えられます。
- 廃病院や廃墟に閉じ込められる
- 出口を探しているうちに、何かが迫ってくる。
- エレベーターが止まらない
- ボタンを押しても止まらず、次々と異様な階に到着する。
- 雪山の山荘での怪事件
- 外は吹雪で逃げられず、次々と人が消えていく。
「正体不明の何かがいるかもしれない」場所に閉じ込められ逃げ場がない状況は本能的に恐怖を感じます。
その心理をうまく利用することで、読者を追い詰めるようなストーリーを作ることができますよ。
怪異との遭遇:理解不能な存在
「怪異との遭遇」は、主人公がこの世のものとは思えない存在と出会い、恐怖に巻き込まれるパターンです。
このパターンの面白さは、怪異の正体がはっきりしないことにあります。
読者は「これは何なのか?」「どうすれば助かるのか?」と考えながら、ページをめくることになります。
たとえば以下のようなストーリー。
- 森の奥に住む異形の存在
- 近づくと姿が見えないのに、後ろから囁き声が聞こえる。
- 鏡に映る「もう一人の自分」
- ある日、鏡の中の自分が勝手に動き出す。
- 無人のはずの家に誰かいる
- 足音が聞こえるたり物が動く。でも誰もいない。
人間は「理解できないもの」に恐怖を感じます。怪異の正体を最後まで明かさないことで、読者の想像力を刺激し、より深い恐怖を生み出せます。
呪いや因縁:過去が生む恐怖
「呪い」や「因縁」をテーマにしたホラーは、ジャパニーズホラーでは古くから愛されているジャンルの一つです。
過去の出来事が影響して、現代にまで恐怖をもたらすストーリーが特徴です。
このパターンでは、次のようなストーリーが考えられます。
- 封印された呪物を見つけてしまう
- 触れた瞬間から怪異に悩まされる。
- 先祖が犯した罪の報い
- 代々続く呪いに主人公が巻き込まれる。
- いわく付きの家に引っ越す
- かつて起きた事件のせいで、家そのものに呪いがかかっている。
このパターンの強みは、「逃れられない運命」を描けることです。
「なぜ呪われたのか?」「どうすれば助かるのか?」という謎解き要素も加えられるので、読者を引き込む物語になります。
精神が歪んでいく:正気を失う恐ろしさ
ホラー小説では「主人公の精神状態が歪んでいく恐怖」を描くこともあります。
主人公の認識が少しずつ現実とずれていくことで、読者も「何が本当なのか」分からなくなります。
物語の語り手を信用できなくなるという小説ならではの怖さを生むことができるパターンです。
- 自分だけが見えているもの
- 周囲の人には見えない「何か」に悩まされる。
- 記憶が改ざんされていく
- 目覚めるたびに、昨日までの出来事が違っている。
- 街全体が異変に包まれる
- 知っているはずの人が全員「知らない」と言う。
これは「自分自身を信じられなくなる」恐怖であり、多くの読者にとって身近で強烈な不安を引き起こします。
日常の崩壊:いつもの世界が壊れる
当たり前に過ごしていた日常生活が、少しずつ異常なものに変わっていく…。
このパターンは読者が共感しやすく「自分にも起こるかもしれない」という恐怖を生む効果があります。
- 家族や友人が別人のように変わる
- ある日突然、家族が「別の誰か」になっている。
- 恋人の性格が徐々に変わっていく
- すぐには気付けないけどじわじわ変化に気づく。
- 学校や職場が異世界に変わる
- 気がつくと、見覚えのあるはずの場所が全く違う雰囲気になっている。
ある日突然変わるパターンと、徐々に変化していくパターンがあります。ほんの少しの違和感から始めることで読者にジワジワと恐怖を感じさせることができますよ。
ホラー小説のタブー!やらないほうがいい書き方
ホラー小説を書くときには「やらないほうがいい」ことがいくつかあります。



小説は自由なものなので「やってはいけないタブー」というわけではありません。
しかし、どんなに怖い設定やストーリーを考えても読者が冷めてしまう展開になってしまうと台無しです。
ここからは、ホラー小説で避けたほうがいい書き方を解説していきます。
- ご都合主義なオチはダメ
- 説明しすぎると怖くなくなる
- スプラッター表現に注意
ご都合主義なオチはダメ
ホラー小説で最も避けるべきなのが「ご都合主義なオチ」です。
それまで怖い展開を積み上げてきたのに、ラストが雑だと読者の満足度が一気に下がります。
たとえば以下のような終わり方をすると冷めてしまいます。
- 全部夢でした
- 超常的な力ですべて解決
- 幽霊ではなく宇宙人でした
こういったオチは、読者をがっかりさせる原因になります。
ホラーの醍醐味は「余韻」です。最後まで怖さを引っ張り、読者の心に残るようなラストを意識しましょう。
説明しすぎると怖くなくなる
ホラー小説では「恐怖の正体を詳しく説明しすぎると怖くなくなる」という落とし穴があります。
- 幽霊の生前の話を長々と説明する
- 怪物の弱点を最初から明かしてしまう
- 登場人物がホラー現象を論理的に解説してしまう
ホラーの恐怖は「わからないこと」によって生まれます。すべてを説明しすぎると謎が解けてしまい、読者が安心してしまうのです。
怪異の正体はあえてぼかし読者に「まだ何かあるかもしれない」と思わせることが大切です。
スプラッター表現に注意
ホラー小説を書くと「もっと怖くしよう」としてグロテスクな描写を増やしてしまうことがあります。
しかし、過剰なグロ描写があると、恐怖よりも「気持ち悪い」が勝ってしまい読者は離脱してしまう可能性が高いです。
前述したように直接的な表現ではなく「ぼかした表現」で想像力を刺激するようにしましょう。
ホラー小説の書き方:まとめ



ホラー小説のストーリーパターンと書き方の基本やタブーを解説しました。
恐怖を生み出す基本を押さえつつ、ストーリー展開や描写に工夫を加えることが大切です。
特に、読者の想像力を刺激するような表現で心理的に怖がらせることを意識しましょう。
また、王道パターンを活用しつつも、独自のひねりを加えることで、読者に新鮮な恐怖を与えることができますよ。