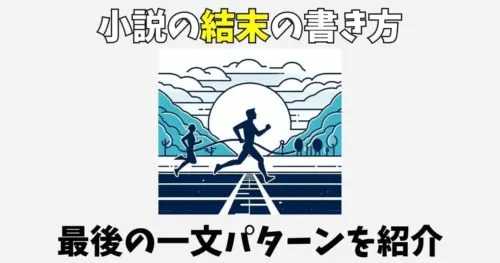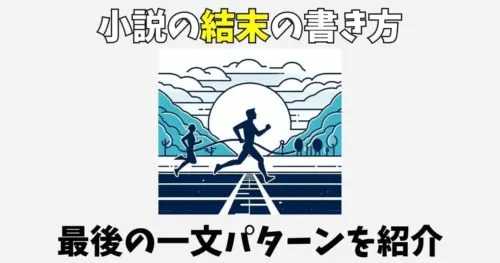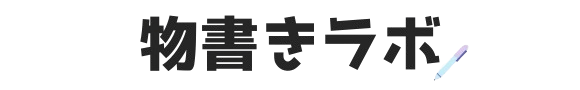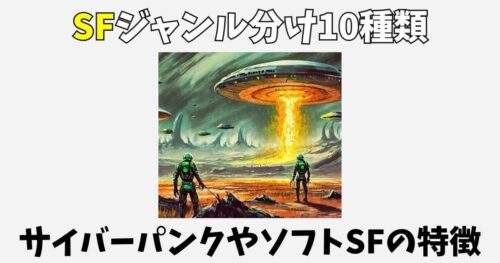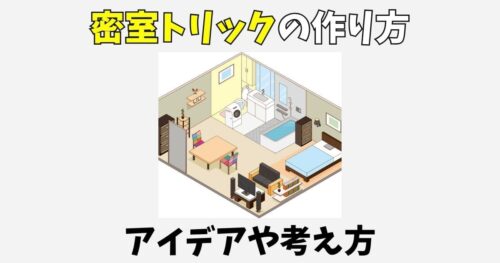小説の終わり方は物語の印象を決定づける重要な要素です。
様々なエンディングがある中で自分が書いた物語には、どんな終わり方が適しているのか迷うことがありますよね。
そこで今回は小説の終わり方の種類を5つ、それぞれの特徴を解説します。
また代表的なハッピーエンドとバッドエンドの書き方を具体例を交えて紹介します。
小説の終わり方5つの種類を解説
小説の終わり方(エンディング)は、物語全体の余韻を決める重要な要素です。
終わり方は単なる物語の締めくくりではなく、作品のテーマを強調したり、読者に考えさせたりする効果もあります。
ここでは代表的な5つのパターンを解説していきます。
- ハッピーエンド:登場人物が幸せな結末を迎える
- バッドエンド:登場人物が不幸な結末を迎える
- ビターエンド:スッキリしない複雑な感情を残す
- メリーバッドエンド:見方によって幸せにも不幸にもとれる
- オープンエンド:結末が明確に示されない
1つずつ詳しく見ていきましょう。
ハッピーエンド
ハッピーエンドは、登場人物たちが幸せな結末を迎える終わり方です。
主人公が困難を乗り越え願いを叶え、愛する人と結ばれるなど読者が「よかった」と思えるエンディングになります。
物語を通じて感情移入している主人公が幸せな姿を見ると読者も満足感を得られますよね。
- 主人公が目標を達成する
- 問題や困難が解決される
- 登場人物たちの関係性が良い方向に進展する
- 読者に希望や前向きな気持ちを与える
ハッピーエンドは読者に満足感を与えるため、エンタメ作品では特に人気のある終わり方のパターンです。
 三雲ハル
三雲ハルもやもやが残らないスッキリした終わり方で万人受けします。
バッドエンド
バッドエンドは、主人公や重要な登場人物が不幸な結末を迎える終わり方です。
目標を達成できなかったり主要人物が亡くなってしまう、大切なものを失ったりするなど、読者にとって悲しいショッキングなエンディングになります。
- 主人公の失敗や敗北が描かれる
- 大切な登場人物の他界や別れがある
- 問題が解決されずに終わる
- 読者に悲しみや衝撃を与える
バッドエンドは読者を暗い気持ちにさせるよくない終わり方のように思えますが、実は強烈な印象を残すことができるため、好む読者もたくさんいます。
また、現実世界の厳しさや人生の複雑さを反映させることで読者を考えさせる効果もあります。



悲しい終わり方だからこそ印象に残り、忘れられない小説になることがあります。
ビターエンド
ビターエンドは、バッドエンドほど悪くないけどハッピーエンドほどよくもない複雑な感情を残す終わり方です。
「ほろ苦い」という言葉がぴったりくるエンディングで、達成感と喪失感が入り混じったり勝利の裏に犠牲があったりするなど、読者にもやもやした感情を抱かせます。
- 主人公は目標を達成するが大きな代償を払う
- 表面上の成功の裏に痛みや後悔が隠されている
- 完全な解決ではなく妥協点が示される
- 読者に「これでよかったのだろうか」と考えさせる
ビターエンドは現実世界の複雑さをよく反映した現実思考な終わり方ともいえます。
「人生には単純な答えがない」ということを表現できるので、大人向けの作品や芸術性の高い作品によく見られるエンディングのパターンです。



すっきりしないからこそ、なんだか心に残る小説になります。
メリーバッドエンド
メリーバッドエンドは、解釈しだいではハッピーにもバッドにもとれるという終わり方。
物語の目標は達成して一見するとハッピーエンドのように見えるけれど、実は登場人物の内面や状況は幸せではないという皮肉なエンディングなどがあります。
- 社会的には成功のように見えて主人公の内面には後悔がある
- 世界を救うけど犠牲を払う
- 読者に「本当の幸せとは何か」を考えさせる
たとえば「魔王を倒したけど実は主人公の父親だった」「海を見るという目標を達成した瞬間に亡くなってしまう」など。
外から見た幸せと、当事者から見た幸せの違いを表現できるので、ハッピーエンドとして描かれていても「これって本当に幸せなの?」と思うようなエンディングになります。



感想を共有したくなる終わり方なのでSNSなどで話題になりやすいです。
オープンエンド
オープンエンドは物語の結末が明確に示されず読者の想像にゆだねられる終わり方です。
「その後どうなったのか」が描かれていないため、読者それぞれが考察して自分なりの続きを考えることになります。
- 物語が完全に閉じずに終わる
- 主要な問いや問題が未解決のまま終わる
- 新たな問題の発生を予感させる
- 読者の想像力や考察を刺激する
有名な小説の例で言うと芥川龍之介の「藪の中」があります。
関係者の証言が食い違うなどして真相がわからないまま終わるという「オープンエンド」になっています。
読んだ人それぞれの解釈ができるので、教材として学校の授業で読んだことがあると思います。
オープンエンドは物語が本の中だけで完結せず、考察する楽しみがある小説です。



読書会などで「あの後どうなったと思う?」と議論が盛り上がるのも、このパターンの魅力です。
小説の終わり方:ハッピーエンドとバッドエンドの書き方
ここからは小説の終わり方の中でも主要なハッピーエンドとバッドエンドについて、それぞれの書き方を解説していきます。
ハッピーエンドの書き方
ハッピーエンドの基本は、主人公や主要なキャラクターが困難や問題を乗り越えて、最後に幸せを手に入れることです。
重要なのはキャラクターが自らの意志で努力した結果、成長して幸せを得ることです。
読者が主人公に共感して応援したくなるように描くことで、ハッピーエンドをキャラと同じ気持ちで喜んでくれるようになります。
ポイント
ハッピーエンドを書くときは以下のポイントを押さえましょう。
- 主人公の成長を証明
- 目標の達成
- 登場人物の幸福
- 読後感の良さ
物語を通じてどう成長したのかを描写で見せます。
たとえば、最初は臆病だったキャラクターが、最後には勇気を持って行動できるようになるといった変化です。
具体例
「勇者が魔王を倒す物語」を例にハッピーエンドの具体例を起承転結で書いてみました。
- 起:平和な世界に魔王が現れ勇者のレオンが立ち上がる
- 承:仲間たちと共に旅をし困難を乗り越えながら成長する
- 転:魔王との最終決戦で苦戦し大ダメージを負う
- 結:仲間と人々の想いが力となり魔王を倒して世界に平和が戻る
困難に立ち向かい最後はクリアするという基本的な構造です。
バッドエンドの書き方
バッドエンドは、主人公が目標を達成できなかったり悲劇的な結末を迎えたりするエンディング。
暗い終わり方ながらも読者の心に強く残るメッセージ性を持たせることが大切です。
単に「悲しい終わり方」にするだけでは読後感が悪くなるだけになってしまいます。
ポイント
バッドエンドを書くときは以下のポイントを意識しましょう。
- 必然性
- 大切なものの喪失
- 社会の残酷さや運命
- 強いメッセージ性
バッドエンドになることが「仕方なかった」と読者に納得させなければいけません。
いきなり不幸な出来事が起きるのではなく、物語の流れの中で自然に発生する悲劇にしましょう。
なぜ悲しい終わり方にするのかを「意図」を持って書くことが大切です。
具体例
バッドエンドの具体例をハッピーエンドと同じテーマ「勇者が魔王を倒す物語」で書いてみました。
- 起:魔王討伐の使命を受けた勇者レオンが旅立つ
- 承:仲間たちと協力して困難を乗り越え魔王城へと向かう
- 転:魔王の正体が人類の闇から生まれた存在だと知る
- 結:絶望の中で敗北し世界は永遠の闇に包まれる
悲しい終わり方でも、読者が感情を解放できるような場面を作ることで読後感が良くなります。
小説の終わり方の種類:まとめ
今回は小説の終わり方の種類を解説しました。
- ハッピーエンドは読者に希望を与え、バッドエンドは深い印象を残す
- ビターエンドは達成と喪失のバランスがあり、オープンエンドは解釈を読者に委ねる
- ハッピーエンドを書くには、努力の末に得た幸せを描くことが大切
- バッドエンドを書くときは納得感のある展開にする
- 物語のテーマや読者に伝えたいメッセージに合わせて終わり方を選ぶのがポイント
小説はどんなエンディングにするかによって、読後感や伝わる物語のメッセージが変わってきます。
大切なのは「なぜそのエンディングを選ぶのか」という意図をしっかり持つこと。
読者にどんな感情を残したいのかを考えながら、納得のいくラストを書いてみてくださいね。