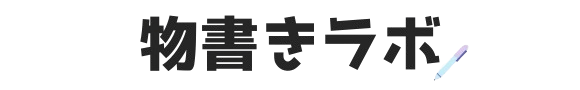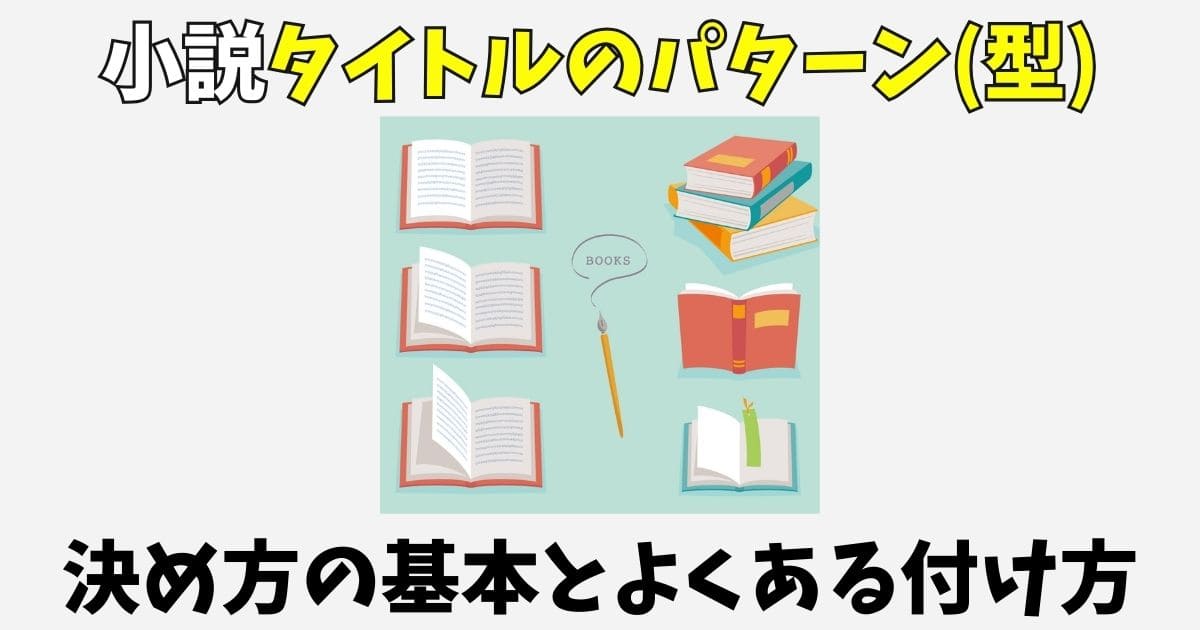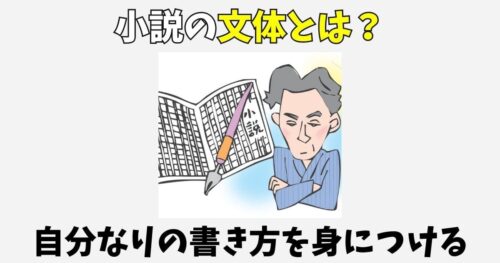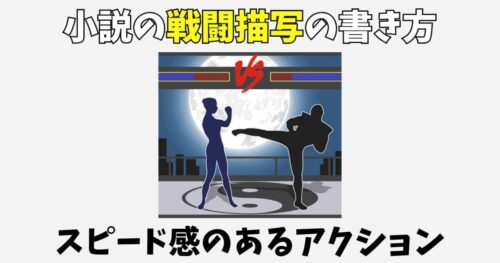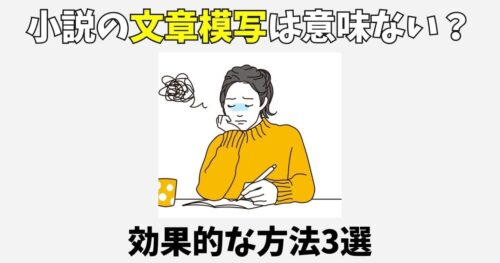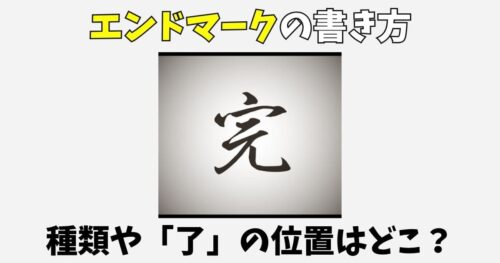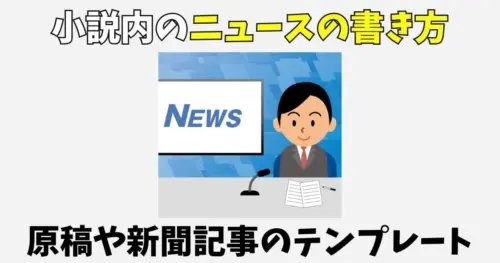小説のタイトルは読者が最初に目にする重要な部分です。
タイトル次第で「読んでみよう!」と思われるか、それともスルーされてしまうかが決まります。
どんなに面白い物語でも、タイトルが魅力的でなければ読んでもらえないこともあります。
そこで今回は、小説タイトルの決め方の基本的な5つのポイントと、思いつかないときに使える9つのよくあるパターンを解説します。
実際の作品を例に紹介するので、悩んだ時に参考にしてください。
小説タイトルの決め方5つのポイント
まずは、小説タイトルを決めるときに意識するべき5つの基本的なポイントを解説します。
- 内容がイメージできるもの
- 小説のテーマを意識する
- 流行りや読者層に合わせる
- 検索で見つけやすい
- おしゃれを意識しすぎない
内容がイメージできるもの
タイトルを見たときに「どんな話なのか」が伝わると、読者は興味を持ちやすくなります。
とはいえタイトルで全て伝えればいいわけではありません。あくまでも「なんとなくジャンルや世界観が伝わる」ことを意識してみましょう。
たとえば、夏目漱石の『坊っちゃん』は主人公のキャラクターをシンプルに表していますし、東野圭吾の『容疑者Xの献身』は、ミステリー作品であることイメージできます。
反対に、『Q&A』のようなタイトルだと、「これはどんな話なの?」とピンとこないかもしれません。
書店でも小説投稿サイトでも、読者がタイトルをざっと見て興味を持ったものだけを読んでみることが多いです。
そのため、タイトルだけで「これはこういう話かな?」とイメージできるようにすることが大切です。
小説のテーマを意識する
小説のタイトルには、その物語の軸となるテーマを反映させるのも効果的です。
たとえば、宮部みゆきの『火車』は、「火車(かしゃ)」という妖怪の名前と、苦しむ人々の姿を重ねたタイトルになっています。
また、太宰治の『人間失格』は主人公の「人間として失格だ」と感じる心情をそのまま表したものです。
テーマをタイトルに反映させると読者が読み終わったあとに「このタイトルがぴったりだ」と納得できるようになります。
タイトルを考えるときは「この作品で一番伝えたいことは何か?」を意識すると、しっくりくるものが浮かびやすいですよ。
流行りや読者層に合わせる
時代によって流行するタイトルの傾向は変わります。
たとえば2000年代後半になると、なろう系ライトノベルでは「長めの説明型タイトル」が流行るようになりました。
例:元勇者のおっさん、転生して宿屋を手伝う~勇者に選ばれ親孝行できなかった俺は、アイテムとステータスを引き継ぎ、過去へ戻って実家の宿屋を繁盛させる
一方で、文学作品や一般小説では『火花』『告白』のように、一語や短いフレーズで印象を残すタイトルが多くなっています。
自分の小説のジャンルやターゲット読者層に合わせて「最近どんなタイトルが流行しているのか?」を調べてみると、読者の目に留まりやすいタイトルを考えやすくなります。
ただし長過ぎるタイトルは覚えにくいデメリットもあるので注意が必要です。
検索で見つけやすい
小説投稿サイトや電子書籍が普及している現在では「検索で見つけやすいタイトル」にすることも大切です。
たとえば『屋根裏の散歩者』のように他に使われていないタイトルをつけると検索したときに、自分の小説を目立つ位置に表示させられます。
逆に、『天使と悪魔』『運命の人』のような一般的なタイトルだと、似たような作品が多いため検索結果に埋もれてしまう可能性があります。
もしタイトルを検索したときにほかの作品がたくさん出てくるなと感じたら、独自性のある単語を足してみるのも良い方法です。
タイトルを決めるときは一度ネットや小説投稿サイトで検索してみて、「他の作品と被っていないか?」を確認するようにしましょう。
おしゃれを意識しすぎない
小説のタイトルをつけるときに「おしゃれなタイトルにしたい」と考える人は多いと思います。
しかしおしゃれさを意識しすぎると意味不明で魅力がないものになりがちです。
避けたほうがいいタイトルの特徴は次の通り。
- 長すぎて覚えにくい
- 難しい漢字や造語を使っている
- 英語タイトルで意味が伝わらない
意味が曖昧すぎるものや長すぎるもの、英語タイトルなどは避けたほうが無難です。
たとえば『深淵に咲く薔薇の調べ』というタイトルだと意味がわかりませんよね。なんとなくおしゃれさを醸し出していても記憶に残りません。
おしゃれさや見た目の格好良さにこだわるよりも、伝わりやすさを優先したほうが読んでもらいやすくなります。
小説タイトルの付け方9つのパターン
小説のタイトルを決める際には、いくつかの定番パターンがあります。
ここでは、具体的な9個のパターンを実際の作品タイトルを例に挙げながら解説します。
- キャラクターの名前を入れる
- 舞台を入れる
- 象徴的なアイテム
- 行動や状態を表す
- 数字を使う
- 比喩的な表現
- 感情や心情を表現する
- 疑問形
- 読むと意味がわかる
キャラクターの名前を入れる
キャラクターの名前をタイトルに入れると、その人物が物語の中心であることが明確になります。
- 『涼宮ハルヒの憂鬱』谷川流
- 『ハリー・ポッターと賢者の石』J.K.ローリング
- 『となりのトトロ』宮崎駿
特にシリーズ作品では「主人公が物語の顔」として認知されるので、読者が続編を見つけやすくなる効果もあります。
また、タイトルに名前を入れることで読者に親近感を持たせる効果もあります。
ラノベや児童書でよく使われているパターンです。
名前だけではインパクトが弱い場合は『涼宮ハルヒの憂鬱』のように、性格や状況を表す単語を加えるとより印象的になります。
舞台を入れる
物語の舞台をタイトルに入れるとその作品の世界観をダイレクトに伝えやすくなります。
- 『黒い家』貴志祐介
- 『小暮写真館』宮部みゆき
- 『マスカレード・ホテル』東野圭吾
特にミステリーやホラー作品では、舞台の雰囲気がストーリーの鍵を握ることが多いためタイトルに取り入れることが効果的です。
貴志祐介の『黒い家』はタイトルだけで不気味な雰囲気を感じさせホラー要素があることが伝わりますよね。
読者に「この場所では何が起こるのか?」と想像させることで小説に興味を持たせられます。
象徴的なアイテム
物語の軸となる象徴的なアイテムやモチーフをタイトルに入れることで印象に残るタイトルを作れます。
- 『指輪物語』J・R・R・トールキン
- 『檸檬』梶井基次郎
- 『青い鳥』メーテルリンク
物語の中心となるアイテムが含まれており、そのアイテムがどのようにストーリーに関わるのかを読者に想像させます。
特にファンタジー作品では、重要なアイテムが物語の鍵を握ることが多いためこの手法は効果的です。
また小説に出てくるアイテムは何かしらのメタファーになっていることも多いので、文学作品や寓話的な作品にぴったりです。
行動や状態を表す
行動や状態を表す言葉をタイトルにすることで、物語の雰囲気を伝えられます。
- 『笑わない数学者』森博嗣
- 『眠れる美女』川端康成
- 『走れメロス』太宰治
このようなタイトルは、「なぜ走るのか?」「どうして眠っている?」といった疑問を読者に抱かせることで、興味を引く効果があります。
小説内でその状態になってるシーンがなくても、作品のテーマやストーリーの方向性を暗示することも可能です。
数字を使う
タイトルに数字を使うと具体性が増してインパクトが強くなります。
- 『1Q84』村上春樹
- 『六番目の小夜子』恩田陸
- 『真実の10メートル手前』米澤穂信
数字には具体的なイメージを持たせる効果があり、読者の記憶に残りやすくなります。
また謎めいた数字で好奇心を刺激することも可能です。
比喩的な表現
比喩を使ったタイトルは、文学的な深みを持たせることができます。
- 『舟を編む』三浦しをん
- 『砂の器』松本清張
抽象的な概念や比喩を使うことで小説のテーマを表現する効果があります。
純文学でよく使われている印象があります。
感情や心情を表現する
登場人物の感情や作品に漂っている雰囲気を示す言葉をタイトルに入れるパターンです。
- 『冷静と情熱のあいだ』辻仁成・江國香織
- 『怒り』吉田修一
作品の感情的な要素を強調することで、より共感を得やすいタイトルになります。恋愛小説やヒューマンドラマで効果的です。
疑問形
タイトルに疑問形を入れることで読者の興味を引くことができます。
- 『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』フィリップ・K・ディック
- 『ベルカ、吠えないのか?』古川日出男
- 『継ぐのは誰か?』小松左京
疑問形のタイトルは読者に「その答えが知りたい!」と思わせる効果があります。
たとえば『ベルカ、吠えないのか?』は、犬の名前らしき「ベルカ」と「吠えない」という要素があり、「なぜ吠えないのか?」という謎を提示しています。
読むと意味がわかる
タイトルを見たときには意味がわからなくても、物語を読んで納得するようなタイトルも強いインパクトがあります。
- 『君の膵臓をたべたい』住野よる
- 『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』七月隆文
- 『葉桜の季節に君を想うということ』歌野晶午
一見すると謎めいていますが、小説を読み進めていくうちに意味がわかり読後に深い余韻を残します。
特に『君の膵臓をたべたい』は、「衝撃的なタイトル」として話題になりましたよね。
最初にタイトルを見たとき、「ホラーなの?」と勘違いする人もいるかもしれませんが実際には切ない青春恋愛小説。
タイトルの意味を知ることで、より強い感動が得られるのがこのタイプの特徴です。
小説タイトルの決め方:まとめ
小説タイトルの決め方5つのポイントと、よくあるパターンを解説しました。
- 内容がイメージできるもの
- テーマを反映させる
- 流行りや読者層を意識する
- 検索で表示されやすいもの
- おしゃれよりも伝わりやすさ
小説のタイトルは、読者にとって最初に目にする作品の「顔」ともいえる重要な要素です。
基本を押さえながら、思いつかないときはよくあるパターンに当てはめてタイトルを考えてみてください。