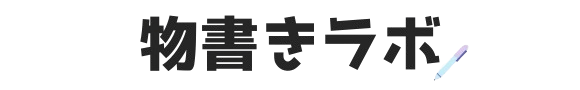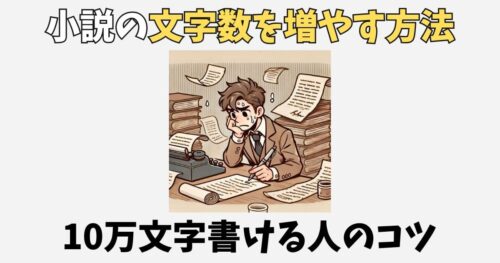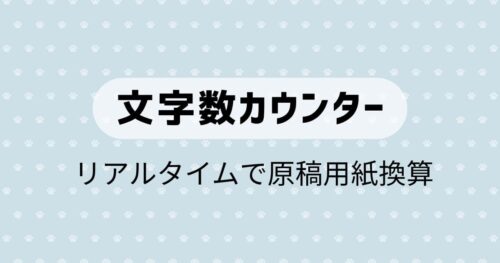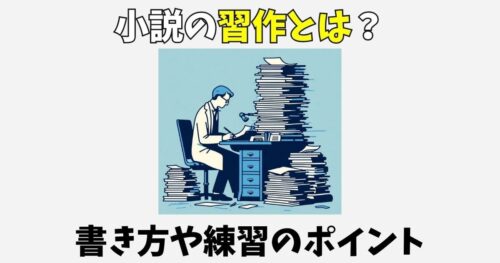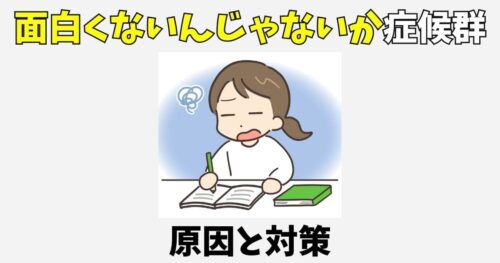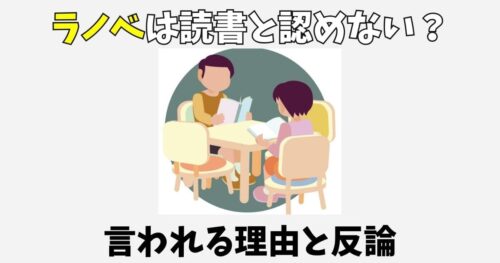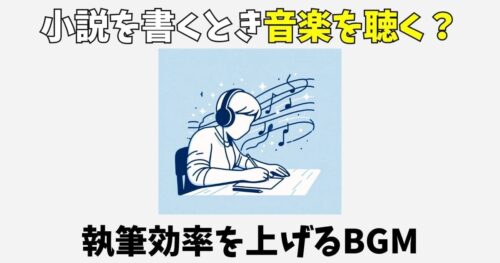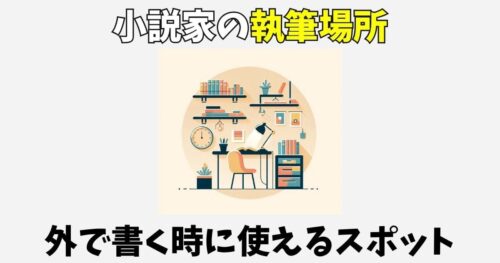小説を書こうとするとき「これってパクリにならないかな?」と不安になることはありませんか?
意図せず真似してパクリと言われてしまうのは怖いですよね。でも創作活動では、何かしらの作品から影響を受けるのはごく自然なことです。
この記事では以下の内容を解説します。
- パクリの基準はどこからどこまで?
- オマージュや二次創作の正しい書き方
- 小説がパクリになってしまうのが怖い!オリジナリティを出す工夫
【小説の書き方】パクリの基準はどこからどこまで?
まずは、パクリの基準について解説していきます。
アイデアや設定、ストーリーなどどこまで真似していいのかどこからがアウトなのでしょうか?
オマージュや二次創作の正しい書き方もお伝えします。
- パクリの基準
- どこからパクリになるのか?
- オマージュはどこまで許される?
- 二次創作とパクリの線引き
パクリの基準
「アイデア自体には著作権がない」と聞いたことがあるかもしれません。
確かに物語の基本的な構造やテーマは多くの作品に共通していて、それ自体は自由に使えます。
たとえば「勇者が魔王を倒す物語」や「幼なじみとの恋愛」などは古今東西たくさんの作品に登場しますよね。
また、小説にはジャンルごとに定番の要素があります。
- ファンタジー:魔法、冒険、異世界、勇者と魔王
- ミステリー:探偵が登場人物を集めて推理を披露、どんでん返し
- 恋愛小説:三角関係、すれ違い、運命的な出会い
これらはどの作品でもある程度共通しているものです。こうした「ジャンルの王道パターン」を取り入れること自体は、パクリではなく「お約束」とも言えます。
小説の基本的な設定やアイデア、テーマだけが似ていてもパクリにはなりません。
どこからパクリになるのか?
ではどこからがパクリと言われてしまうのでしょうか?
パクリと見なされるのは「具体的な表現や要素」が酷似している場合です。
ジャンルの要素を使うのは問題ありませんが、具体的な表現や展開がそっくりになるとパクリ認定されてしまいます。
- 登場人物の性格や設定
- セリフ
- 文章表現
- プロットの展開
これらの具体的な要素がほぼ同じだと「この小説パクリだな」と言われてしまう可能性が高くなります。
小説のように作者が自由に表現する創作物の場合、どこからどこまでがパクリという明確な線引というのは難しいですが、以下のようなケースはアウトになると言えます。
- 文章の丸写し
- 原文をそのまま、もしくはわずかな言い換えで使用
- キャラクター設定の完全な流用
- 名前を変えただけで、性格・外見・背景が同一
- 人間関係まで同じ
- ストーリー展開の完全なコピー
- 起承転結の流れが同一
- 重要な場面展開が酷似
一部分だけが似てるだけなら、偶然一致してしまったという見方もできますが「全体として見て」明らかに似てると認められるとパクリになります。
 三雲ハル
三雲ハル部分的なら意図せず似てしまうことはあっても、大半が偶然似ることはないという判断がされてしまうわけです。
オマージュはどこまで許される?
パクリと混同されやすい言葉に「オマージュ」や「インスパイア」があります。
これらはパクリと違い、過去の作品に敬意を表しつつ自分の創作に活かす方法です。
しかし明確に元ネタがあるため、書き方を間違えるとパクリと言われてしまう可能性があります。
オマージュとインスパイア
どのように使えば「パクリ」ではなくオリジナルの創作として認められるのでしょうか?
そもそもオマージュとインスパイアは以下のようなものです。
- オマージュ
-
ある作品への敬意を込めて特徴的な要素を取り入れること。
元ネタが明確で、ファンに「これはあの作品のオマージュだ」と伝わるようにするのがポイント。
- インスパイア
-
作品からアイデアや雰囲気のヒントを得て、新しい物語を生み出すこと。
たとえば「この小説の世界観が好きだから似たような雰囲気の作品を書いてみたい」と考えるのは問題ない。
パクリとの違いはオリジナル作品への敬意が感じられるかどうか、独自性やオリジナリティが加えられているかどうかがポイントとなります。
「影響を受けているがまったく別の作品として成り立っている」場合はパクリになりません。
たとえばハリー・ポッターの影響を受けた魔法学校の物語を書いても、それが独自のキャラクターや設定を持っていれば問題にならないのです。
元ネタがわかること
オマージュで重要なことは元ネタが明確であること。
読者が小説を読んで「これはあの作品をオマージュしているな」とわかるようにしないといけません。
自分では敬意をもって真似したと思っていても読者に伝わらなければパクリと代わりません。
元ネタがわかるようにするためには、誰もが知っている作品をオマージュすること。
芥川龍之介や太宰治などの古典文学や、ハリーポッターやスターウォーズなど世界的に知名度があるものなら真似しても読者が気づいてくれます。
一方、好きだからといって知名度がないWeb小説をオマージュしても誰も元ネタに気づいてくれません。ただのパクリと言われてしまうでしょう。
二次創作とパクリの線引き
小説を書いていると人気作品の二次創作を書きたくなることもありますよね。しかし、二次創作にはルールがあるので注意が必要です。
まず前提として、作品によっては公式が二次創作を禁止している場合があります。しっかりと規約を読んで許可されているか確認しましょう。
許可されている場合は「二次創作ガイドライン」が公表されていることが多いのでしっかり守ること。
二次創作を書く場合は、原作のセリフやストーリーをそのまま使用するのはパクリになります。
あくまでも原作をもとに公式のルールを守りながらオリジナル要素を加えて書きましょう。
小説がパクリになってしまうのが怖い!言われないための書き方
自分ではパクっているつもりはないのに、小説を書いていると自然に誰かの作品に影響を受けて真似してしまっているかもと不安になることがありますよね。
パクリと言われてしまうのは小説家にとってとても怖いことです。
ここからはパクリと言われないオリジナル作品に仕上げるための書き方を解説します。
- 複数の要素を組み合わせる
- 自分の経験を取り入れる
- 設定を具体的にする
複数の要素を組み合わせる
オリジナリティを出すには発想を広げることが大切です。
よく「完全に新しいアイデアなんてない」と言われますが、それでも組み合わせ次第で新しいものは生み出せます。
たとえば「SFと江戸時代」や「ファンタジーと探偵モノ」など、異なるジャンルやテーマを組み合わせることで新鮮なアイデアになります。
「異世界転生もの」は一般的ですが「異世界転生したら歴史上の偉人になっていた」など、ちょっと変えるだけで物語のパターンは広がっていきます。
自分の経験を取り入れる
どんなに似てる設定でも「自分が見てきた世界」を反映させると独自の作品になります。
自分が経験してきたことや感じたこと、それらによって積み上がってきた価値観は自分にしかないオリジナル要素です。
たとえば、同じ「学園モノ」でも自分が体験した学校生活のエピソードを織り交ぜるだけでぐっとオリジナリティが増してリアルになります。
設定を具体的にする
「設定が似ている」と言われることを避けるには、細かい部分で差別化を意識することが大切です。
- 世界観のルールを変える
-
たとえば、「魔法が使える世界」ではなく「魔法が使える代わりに寿命が削られる世界」にするなど、ルールを加えるだけで印象が変わります。
- 文化や社会の仕組みを独自に考える
-
「王国が舞台」なら「国王は1年ごとに投票で変わる」など、普通と違うルールを加えるとオリジナル性が増します。
- キャラの個性を掘り下げる
-
「冷静沈着な剣士」ではなく「料理の話になると饒舌になる冷静沈着な剣士」にする。
最初に思いついた設定をさらに掘り下げて具体的にしていくことで、ありがちな設定からオリジナリティを高められます。
小説のアイデアが被るのは仕方ないと言われることもありますが、細かい部分で独自性を出せばまったく違う作品に仕上げることができますよ。
パクリと言われない小説の書き方:まとめ
小説のパクリの基準はどこからどこまでなのか、オリジナリティを出すための書き方を解説しました。
- アイデアや基本的な設定はセーフ
- 具体的な表現を真似するとアウト
- 二次創作は公式のガイドラインを確認する
- オマージュは元ネタがわかることが重要
- オリジナリティを出すには、設定を組み合わせたり自分の経験を取り入れること
これまでに数多の作品が発表されている以上、小説を書くうえでパクリと言われてしまう問題は避けて通れません。
基本的なルールを守って執筆を楽しみましょう。